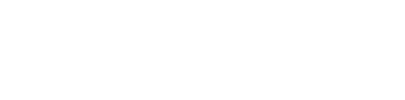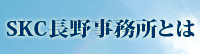30年入試情報
長野県の現状と問題点
30年の長野県の東大京大の現役合格は東大14名(長野5、屋代3、松本深志・上田・伊那北・松本秀峰、佐久長聖・長野日大1)京大8名(松本深志3、長野・上田・飯田・佐久長聖・長野日大1)です。東大と京大合わせて22名、昨年の34名から大きく減少しました。今年は高校入学時に全国のトップレベルと戦える学力のある生徒が少なかった・・・東大京大入試、それは学校の指導ではどうにもならない「現実」なのです。それに対して国立医学部入試はセンター試験で9割得点を取れば受かる、よって高校の指導力がストレートに現れます。県内の医学部志望者は一部の特別にこだわりのある生徒以外は信大医学部医学科の推薦入試を第1の選択肢にします。二次試験免除でセンター試験のボーダーラインも低い、しかしここで大きな問題があるのです。昨年29年入試のリンク「医学部推薦入試」のページに書きました。13年前に始まったこの「地域枠制度」に学力低下の大きな落とし穴があります。長野県内の国立医学部の現役合格者は15年20前と比較して半減しています。それは校内推薦を獲得するためには3年間定期試験を勝ち抜かなければならない、長野高松本深志高には高校入学時に医学部志望者が50名から100名います。それぞれ学区内には中学が約50校さらに信大附属中があります。長野深志校内上位50番の生徒たちのほとんどが中学では1番2番だった定期試験得意の生徒たち、各校の代表4名の座をつかむには本当に3年間大変な思いをしなければならないのです。そして定期試験を勝ち抜き、晴れて校内代表になっても全員が85%を超えることができない、定期試験中心の学習が真の学力になっていないのです。推薦を獲得できなければとても一般受験では勝負できない、そして1年浪人しても簡単ではない、県内の予備校での医学部医学科の合格率は医系コース在籍者の1割以下です。一方で最初から推薦は狙わないで、定期試験に追われることなく「自分の勉強」を3年間続け、一般受験で医学部現役合格を勝ち取る利口な生徒も少数います。
定期試験対策、SKCでは「暗記コンテスト」と呼んでいます。特に長野高は2期制で2年次は前期3回後期3回プラス春・夏・冬の休み明け課題テスト(整理考査)3回、何と年9回ほぼ毎月ある、とても負担が大きい、テスト対策に追われあっという間に1年2年が過ぎてしまうのです。大量の課題を与えてはテストの繰り返し、トップレベルの生徒たちはうまく対処していますが9割の生徒たちにとっては学力上昇の大きな妨げになっていることに教師たちは気づいていないのでしょうか。さらに年3回の進研模試さらに駿台模試そして学年末には河合塾の模試まで受けさせる、年9回の定期試験に加えて5回6回の全国模試、異常です。当然年間スケジュールがタイトになる、結果、春・夏には「特編授業」と称して登校させられる、春休み夏休みが極端に短くなり「自分の勉強」をする時間が十分に取れないのです。都会の進学校との一番の違いは年間の休日数の違い、夏休みは7月20日前後に始まり8月末までが一般的です。長野県の進学校では休日短縮の「過重労働」が常態になっている、生徒は毎月毎月のテスト対策に追われ疲れています。昨年広告で全く前期後期の切れ目のない高校での2期制には問題ありと指摘しておきました。開成高校は3学期制、1学期の復習を夏休み、2学期の復習は冬休み、3学期また年間の復習は春休み、この3期制はとても合理的です。2期制は9月秋休みの大学でのサイクル、高校では合いません。開成では定期試験は中間・期末の年6回に実力テスト1回、とてもシンプルです。全国模試を学校でやることはありません。生徒は自分の勉強をする時間を十分与えられています。社員には休息をしっかり与え、よい仕事をして業績を上げてもらいたいと考えている一流企業をイメージします。開成高校は今年も東大合格者1位、37年連続日本一ですがその最大の要因は東京の「男女御三家」6校のうち唯一高校受験で100名入学させている制度にあります。この「高入組」が東大合格者数を押し上げている、入学時には英語の学力はセンター試験で9割得点できるレベル、高校入学時にすでに勝負がついています。実際、長野県内にも開成高校合格レベルの高1生が毎年10名程度いる、昨年松本から開成高校へ電車通学をしている生徒がいることを紹介しましたが、この生徒たちが東大現役合格するのです。